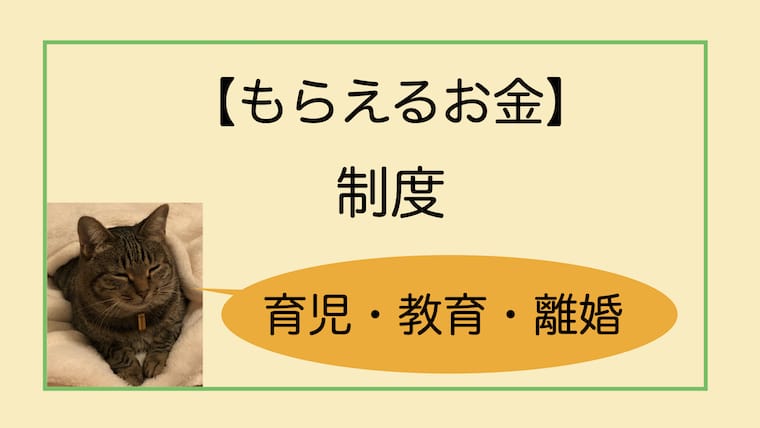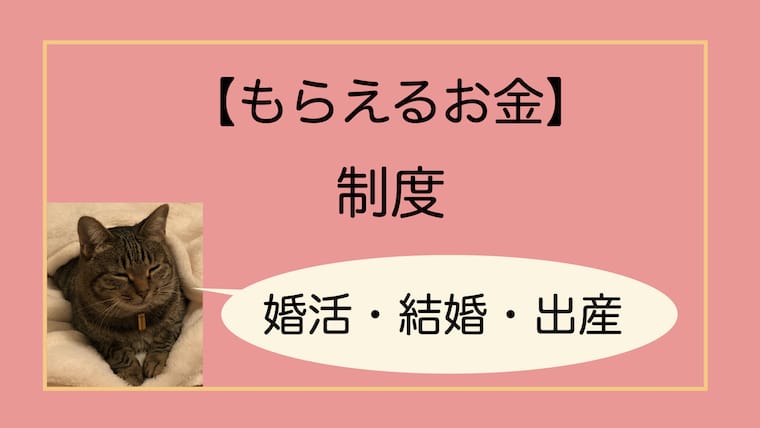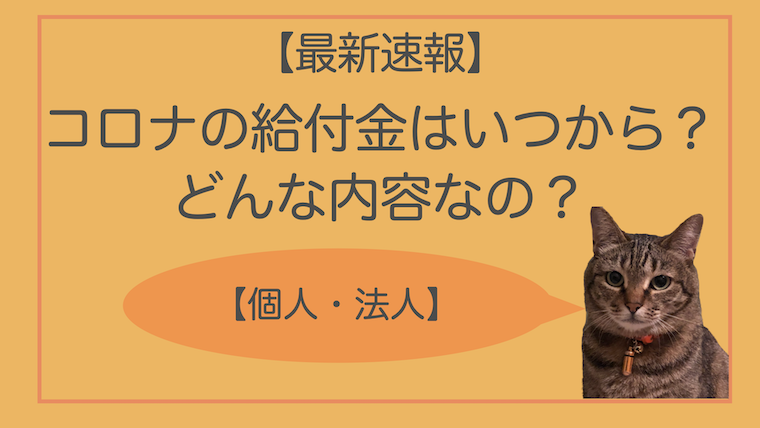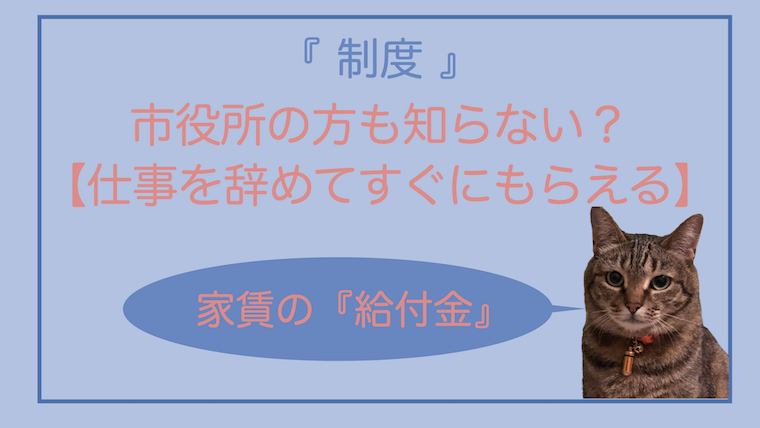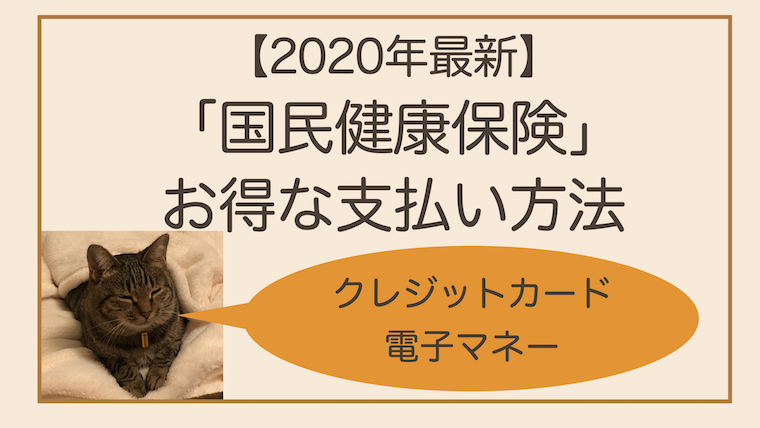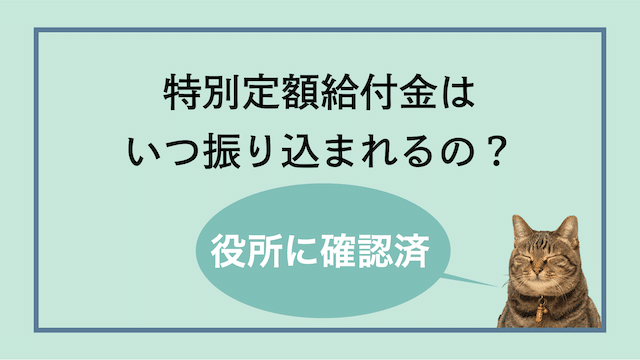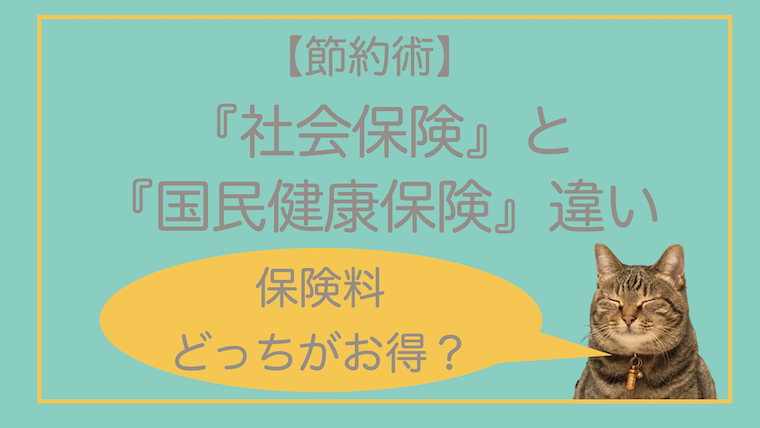
日本すべての国民は、勤務先の「社会保険」または「国民健康保険」の医療保険に加入することが義務付けられていますね。
これは『 国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)』という
病気や怪我といった保険事故に遭遇しても安心して医療を受けられることを目的とした制度によるものです。
本質としては、国民がお互いに保険料を出し合ってお互いを助け合おうという相互扶助の精神が根底にあります。
その真意を知らないままだと、
「どうして病院にも行かないのに高い保険料を支払わなければならないのだろう?」
と考えてしまうと思います。
実際に自分もそうでした。
理由は理解できますが、現実問題として保険料が高い!と思っている方も多いのではないでしょうか?
中には「借金」をしてまで支払うという人もいます。
「社会保険」と「国民健康保険」にどのような違いがあるのでしょうか?
また、少しでも節約する方法はないのでしょうか?
本記事では市役所の方に確認を取った実体験をまとめます。
- 社会保険と国民健康保険の違いについて知りたい
- どちらに加入した方が安いのか知りたい
- 節約する方法について知りたい
このようなお悩みにお答えします。
先に結論から述べますと
条件を満たす健康保険に加入する義務があり、料金も変わってきます。
仮に切り替えの手続きをしなかったとしても遡っての請求がありますが、保険料を節約する方法があります。
結論は上記の通りですが、詳しく本記事にて解説していきます。
保険料の為にわざわざ借金をして支払っている知り合いがいますが、その借金は自らの首を締める事に繋がります。
一人でも多くの方が、そのような状況に陥らないようになれたらと思います。
『本記事の内容』
Ⅰ:「社会保険」と「国民健康保険」の違い
Ⅱ:「社会保険」と「国民健康保険」どっちがお得?
Ⅲ:保険料を節約できる方法
上記についてまとめていきます。
本記事をお読みいただくと、それぞれの保険について知ることで無駄な出費がある場合に節約することができます。
 フミフミ
フミフミ 保険料は高いから節約できるときはしておくニャよ!
「社会保険」とは
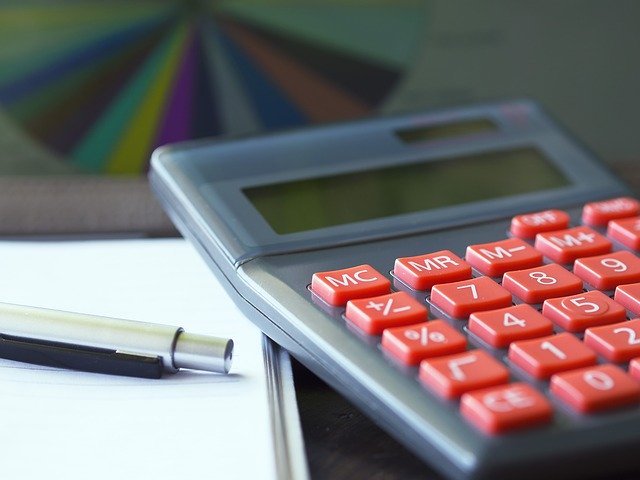
- 年金保険
- 健康保険
- 介護保険(40〜64歳)
- 労災保険
- 雇用保険
すべて基本的に強制加入になります。
広い意味だと5つの要素がありますが、狭い範囲ですと以下になります。
- 年金保険
- 健康保険
- 介護保険(40〜64歳)
を「社会保険」
- 労災保険
- 雇用保険
を「労働保険」(労災保険、雇用保険)と区別して使われています。
保険料は、被保険者1人で負担するものではなく、「事業所」と「被保険者」が折半する形で支払います。
「国民健康保険」とは

国民健康保険料=「医療分」+「支援分」+「介護分※」となります。
※被保険者に該当する人(40歳~64歳)の国保加入にだけ賦課(課税)される項目です。
39歳以下および65歳以上74歳以下の人には賦課(課税)されません。
保険料は、「世帯主」が被保険者全員の合算した金額を支払います。
「医療分」
国民健康保険の加入者の医療費などに充てられ、全員が負担する保険料です。
(年間の医療分保険用には、各市区町村ごとに最高限度額が設定されています。)
「支援分」
後期高齢者の医療費の一部を負担するために国民健康保険に加入している全員(0歳から74歳まで)が負担する保険料です。(年間の医療分保険用には、各市区町村ごとに最高限度額が設定されています。)
支援分=「均等割」+「所得割」+「平等割※」となります。(※平等割は負担のない市区町村もあります。)
「介護分」
介護保険制度(お年寄りや寝たきりの方など、介護が必要になった方が安心して介護サービスを利用できる制度)の介護納付金として、40歳〜64歳までの方が負担する保険料です。
(年間の介護分保険料には各市区町村ごとに最高限度額が設定されています。)
介護分=「均等割」+「所得割」+「平等割※」となります。(※平等割は負担のない市区町村もあります。)
「社会保険」と「国民健康保険」の違い

①運営母体の違い
②加入条件の違い
③扶養に対しての扱い方の違い
④保険料の算出方法の違い
①運営母体の違い
・社会保険:「協会けんぽ」や「各社会保険組合」が運営を行っています。
・国民健康保険:「市区町村役場」が運営を行っています。
運営の母体が違うので、「加入条件」、「扶養に対しての扱い方」、「保険料の算出方法」などが違ってきます。
②加入条件の違い
社会保険
- 勤務先が社会保険の適用事業所になっている
- 勤務先に常時雇用されている
平成28年10月より社会保険の適用範囲が拡大されて、短時間労働者でも次の加入条件を満たすことで、社会保険に加入できるようになりました。
- 勤務先の従業員数が501人以上
- 1年以上の雇用が見込まれている
- 1週間の労働時間数が20時間以上
- 賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)
- 学生ではなく、70歳(75歳)未満である
国民健康保険
・現在企業に勤めていて、すでに社会保険に加入している人。または、世帯主が社会保険に加入していて、その扶養に入っている家族
・現在生活保護を受けている人
※この条件を満たす人以外は『 強制加入』となります。
 フミフミ
フミフミ 「働いている人」も「働いていない人」も保険料を支払う対象になるということニャね
③扶養に対しての扱い方の違い
社会保険
対象者:被保険者の妻・子供・父母
年収:130万円未満、被保険者の年収の半分未満
被保険者の一人分の保険料で、扶養家族の人数分の保険証を交付してもらえます。
 フミフミ
フミフミ 扶養範囲内で働きたいという人が増える理由ニャ
国民健康保険
加入する人数分の保険料を納めなければなりません。
前年の年収と世帯人数によって算出される為、保険料が高くなる傾向にあります。
④保険料の算出方法の違い
社会保険
・年齢や現在の給与額が元になります。
・都道府県ごとに保険料額表が決められています。
企業が半分負担してくれますので、実際には『保険料の半分』になります。
 フミフミ
フミフミ 「労使折半」になるのが特徴だニャ
国民健康保険
上限:54万円
市区町村によって異なりますが、加入者の前年の所得や世帯人数などによって算出されます。
保険料は、所得割・均等割・平均割の合計で算出されます。
国民健康保険とは別に『介護保険料』の支払いがあります。
算出方法は、国民健康保険と同様で、所得割・均等割・平均割の合計です。
前年の所得が元になるため、企業を退職した後に起業して安定収入が得られないうちに「社会保険」から「国民健康保険」に切り替えると、保険料の負担が大きくなる可能性があります。
 フミフミ
フミフミ 次に紹介する『任意継続』という方法もあるニャ!
「社会保険」と「国民健康保険」どっちがお得?
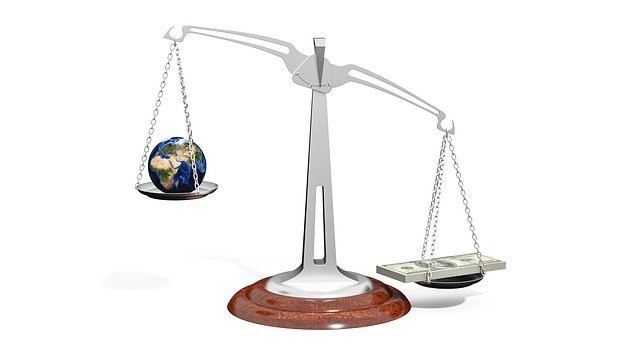
「社会保険」と「国民健康保険」が切り替わるときは、『退職』・『就職』する時になります。
その際に、扶養家族の条件から保険料が跳ね上がることがありますので、『任意継続』という方法を検討すると良いでしょう。
※退職後20日以内に手続きをする必要があります。
 フミフミ
フミフミ これだと急に保険料が上がることもないニャ
ここからは具体的な例を見ながら検証していきます。
社会保険加入者から個人事業主へ
<例1>
・家族構成:夫30歳、妻30歳、子供3歳の3人家族
・国保加入者人数:3人
・所得:夫300万(給与のみ)、妻0円、子供0円
・住居:東京
今までの社会保険料は事業所との折半ですので、月額:11,844円でした。
年間で142,128円です。
「社会保険」➡︎「国民健康保険」
国民健康保険料=「医療分」+「支援分」+「介護分※」となります。
※被保険者に該当する人(40歳~64歳)の国保加入にだけ賦課(課税)される項目です。
39歳以下および65歳以上74歳以下の人には賦課(課税)されません。
「給与所得控除の金額」は年収 × 70% – 18万円で出します。
300万円 × 70% – 18万円 = 192万円となることが分かります。
「基準額」は給与所得控除後の金額から33万円を引くので、
192万円 – 33万円 = 159万円となります。
「医療分」は、「所得割」+「均等割」+「平等割」で出します。
所得割=基準額(159万円)× 5.85%=93,015円
均等割=加入者の人数(1名)× 29,823円=89,469円
平等割=世帯 × 2,426円=2,476円
- 医療分=93,015+89,469+2,476=184,960円
「支援分」は「所得割」+「均等割」+「平等割」で出します。
所得割=基準額(159万円) × 1.91%=30,369円
均等割=加入者の人数(1名) × 10,331円=30,993円
平等割=世帯 × 827円=827円
支援分=30,369+30,993+827=62,189円
国民健康保険料=医療分(184,960円)+支援分(62,189円)=247,149円
参照:国民健康保険
「社会保険」➡︎「任意継続」
任意継続にすると月23,688円になります。
年間は284,256円です。
結論
国民健康保険料:247,149円
任意継続:284,256円
を計算すると、国民健康保険の方が37,107円安いという結果です。
社会保険加入者から転職する場合
<例2>
・家族構成:夫30歳、妻30歳、子供3歳、1歳の4人家族
・国保加入者人数:4人
・所得:夫300万(給与のみ)、妻0円、子供0円
・住居:東京
退職後、次の企業での社会保険に加入することができれば、その企業での手続きに則ることになります。
しかし、転職先が社会保険適用事業所でなかったり、退職後転職先が決まっていないという場合には、例1と同様に、国民健康保険か任意継続の手続きをする必要があります。
今までの社会保険料は事業所との折半ですので、月額:11,844円でした。
年間で142,128円です。
「社会保険」➡︎「国民健康保険」
次は4人家族の例ですが、上記で計算式をまとめているため、簡潔にまとめていきます。
医療分:214,783円、支援分:72,520円となります。
合計:年間287,253円となります。
「社会保険」➡︎「任意継続」
任意継続にすると月23,688円になります。
年間は284,256円です。
結論
国民健康保険料:287,253円
任意継続:284,256円
計算すると任意継続の方が、2997円安くなります。
 フミフミ
フミフミ 国民健康保険は扶養家族が増えるほど高くなるニャ
国民健康保険(税金)などのお得な最新決済方法はこちら【還元率が違う!!】
保険料を節約できる方法

「国民健康保険」にするか「任意継続」にするかの選択は上記で解説した通りです。
計算してどちらが安くなるのか考えることで節約に繋がります。
もう一つ節約に繋がる方法がありますのでまとめていきます。
「社会保険」➡︎『未加入』パターンです。
具体的には、退職後や離婚などで扶養から外れた後に国民健康保険に加入せず、未加入のままという状況です。
実際に退職して収入がないのに国民健康保険を支払えるかというと払えないという方も多いです。
国民健康保険の時効
国民健康保険には時効がありますので結果的に支払わなくてよくなることがあります。
時効は下記のとおり、国民健康保険料と国民健康保険税で異なっています。
| 国民健康保険料の場合 | 2年間までさかのぼって請求される |
|---|---|
| 国民健康保険税の時効 | 5年間までさかのぼって請求される |
(※国民健康保険料または税については、各市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村HPをご確認ください。)
つまり、国民健康保険に3年間未加入から加入した場合は、2年間分は支払う必要がありますが、1年間分は免除という形になります。
ただ、2年間分でもかなりの金額になります。
 フミフミ
フミフミ 次の方法でリセットできるニャ
国民健康保険の未加入期間分を免除する
①誰かの扶養に入る
②就職して社会保険に加入する
結婚して夫や妻。もしくは家族の扶養に加入することです。
健康保険の条件にもよりますが、同居していなくてもOKな場合があります。
市の方では退職日、社会保険の加入日は分かっても未加入期間について正確に確認できないとのことでした。
その為、就職して社会保険に加入した場合は、さかのぼっての未加入期間の請求はないので免除される形になります。
 フミフミ
フミフミ 病院では全額負担になることは忘れてはいけないニャ
まとめ
「社会保険」「国民健康保険」の違いは主に扶養の扱い方や、社会保険だけは会社が半分負担してくれるという点に大きな違いがありました。
退職や起業の際には、「国民健康保険」か「任意継続」になるかで料金が変わりますので計算するか役所に相談することをオススメします。
また、どうしても国民健康保険の未加入期間の金額がさかのぼっての請求のため、高額になってしまいます。
誰かの扶養に入るか、社会保険に加入することで免除になりますので参考にしてみてください。
退職した時に使える給付金制度はこちら